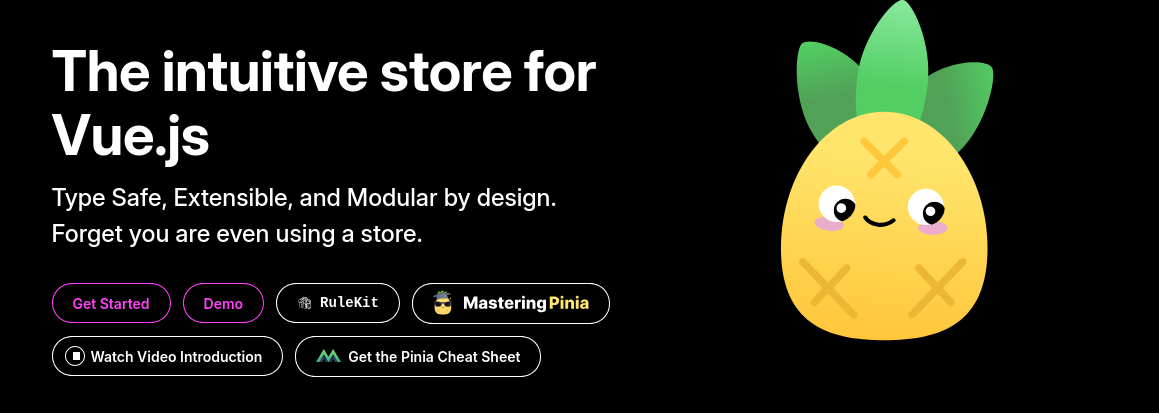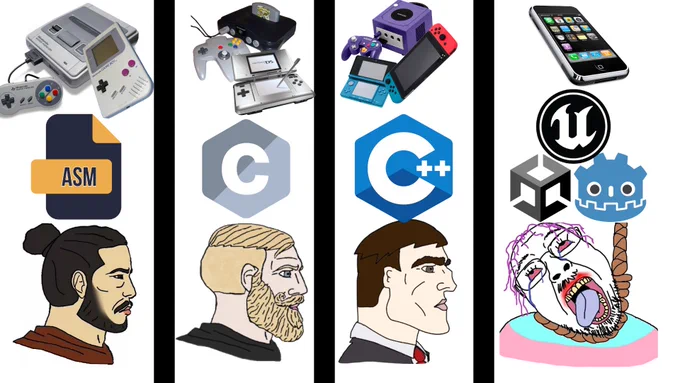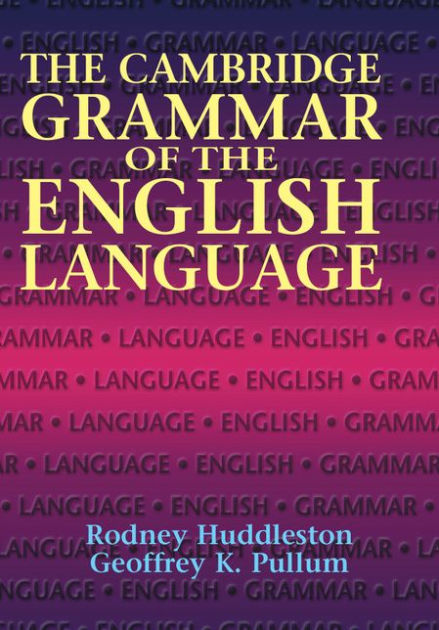夜報
nitter.netが復活してた。なにか存在が反抗的なので好き。もはや使わないけど。
しかし、結局はRSShubが生き残ると思う。世界をRSS化するプロジェクトでときめきを感じて欲しい。
私はこれのヘビーユーザーなのでおすすめします
piniaもrsshubもvitepressを使ってサイトを作ってる。
§
橋本麦氏がローカルのスクボの原型を作っている! 私もこうならなくては…
https://baku89.com/ja/source-cosense
プログラマカブルなドローツール作っていたり、私の興味の先を行っていて動向が気になる人物
透視したところ、NuxtとVueとPiniaを使っている。
Nuxtはデザインが一番モダンでかっこいい(中二)。 Piniaは初見だった。
このサイトのhugoのbearは最速だから使ってるけど、静的サイトでコセスできるならそれが一番だ。 脱法はてなブックマーク(トピック指向のタイムライン)作りたいね。十年後に取り組みます。
食
サプリを使い始めて、生活習慣の倦怠感とは完全に無縁となった。 というか旧態依然の食生活をする意味が分からくもなった。
なぜなら食生活の目的は栄養素の定期的な摂取であり、食物を口に含むことではないからだ。 薬とサプリの違いもここにある。薬は局所的な目的のための合成物で、サプリは栄養素の抽出である。
そして市販されている食品は砂糖と食物油だらけ…私にとってスーパーは小岩井生ヨーグルトの専門店である。
よくエナジードリンクが健康に悪いと言われるが、それは添加物や砂糖が入っているし、含有量を考えず、ジュースとして飲むから不健康なんだ。 粉状のサプリに手を出した時、つまりオリジナルブレンドのエナジードリンクを作り出した時、サプリはその真価を発揮する。 私が好きなタウリンもエナドリによく含まれてる。それと一緒に砂糖を飲みたくないんだ。価格的にもタウリンの方が安い。エナドリ買う意味は全く無い。
ただ肉食が以前として有効なのは、摂取方法によって、吸収率が異なるからです。本当はサプリを使わない方が良いのだけど、そんな天然素材だけ集める術を資金力を時間を持たないため、サプリが最善手だと思う。
私のスタメン
- タウリン
- レクチン
- クレアチン
- イノシトール
- グリシン
私に効果があったモノ、プラセボ効果を抜きに判断する材料として、長時間の作業の結果を比較することが一番良いと思う。 タウリンで言えば、2g摂取すると一日中歩き回っても、疲労感が不快に思わなくなる。脳や体が疲れることからは避けられないので、思い込みかどうか測るための手段として有効だ。山にある神社とかに行ってください。
作業用
昔から貧血で、血の気が引いてる時とそうじゃない時の違いを感じることが多かった。体はその時々において状態を変える。以前まで長時間の作業ができなかったのも、この揺れに対応することが難しかったからだ。 最近は宣言して、宣言通りに作業が行えるようになった。仕事みたいな強制される場合は可能なんだけど、それ以外に、つまり「自主的に過労死する方法」についてよく考えている。
現状はアッパー系のサプリを逐次投入するという力技が有効だと思った。 よくコーヒーが使われてる印象がある。しかしカフェインは致死性が高く、副作用が大きいので少量にしたほうが良い。
- チロシン
- カフェイン
これらを1日の許容量を分割して、例えば「30分ごとに少量摂取する」ようなことをしてる。ここは自分にあった方法が見つかっていない。 カフェインを取りすぎるとたまに精神が漆黒状態になるので避けたい。
腰に付けられるベルトで試験管を持ち歩いて、定期的に500mg摂取したい。こてこての錬金術師みたいに
便秘対策
ぶりぶり
- フレックスシード
- 食物油不使用、非中国産のミックスナッツ
かなり重要、ミックスナッツでもかなり有効だった。
まとめ
前にも書いたが、不健康な食生活なのに、不機嫌になって不快に思う人というのはセルフネグレクトなのだ。 太っている人が怒っているのを見るたびに、炭水化物や食物油を取らなければ(少なくとも今よりは)良い気分で生きられるのに…と思う。 なぜ人は自分の口に含むもので楽しんでしまうのか。
それでもスーパーで売られているパッケージされた商品を食事だと思っている人が多数派なのは、皆が認めるところの陰謀だよな。
「健康=気分が良い」そして気分が良いことは自分にとって良いことだし、作業効率が上がる。(逆に食生活がボロボロでも有能な人物は怖い。) これを飲み込める人は意外に少ないと思う。自分に酔うことをどこか自分に許してしまう。これが自傷の始まりです。
ゲーム語り
void strangerやouter wildを含める傑作と言われるゲームだけど、客観的に傑作だと理解できるのに、私はなぜか良いと思わなかった。 言語化したり評価したり、相対軸は良いことは理解するが、絶対軸を参照すると面白くない/良いと思わない。 評価する語彙はなんでもいい<任意のスコア>が低い。
精神が安定し成熟した大人は界隈に所属しない
のでまるでゲーマー振って「有ること自体を有難がる」ことはせず、総じてつまらない場合はありのままを受け止められる。究極的にゲームそのものがつまらなくても全く問題ない。
なぜ理性的に傑作だと理解すたゲームが面白くなかったのだろう?と思ったときに、ゲームは近視眼的な評価がされるのだと思う。 ゲームはゲームとしか比較されないんだ。
わかりやすくすると、「野獣七変化による連続モーフィング」と「量子の月」のアイデアはどっちが優れいてると思う?
私は、正直、残念ながら、素直に言うと、不本意ではあるんだが、「野獣七変化による連続モーフィング」の方が優れたアイデアだと思うし、単純な面白さで言えば上だと思う。文化的なコンテクストも上だ。
野獣七変化による連続モーフィングとはこれ
面白くなることに節操がなくて、素晴らしすぎる…
「観測するまでどっちか分からん」みたいなシュレディンガーが悪い例えとして紹介した猫箱から派生した解釈を未だに誤用してる時点で「量子の月」のアイデアはガキ向け。
猫箱は使われたのは「巨視的な例で量子を説明することは間違い」であることを説明するためなんだよな。
https://www.mathematik.uni-muenchen.de/~schlenga/SS16/Material/SchroedingerDE.pdf
猫は箱の中で死んだか否かは古典物理学が適用されているのに、ある一定の相になると、二重スリッド実験のように古典物理学が通用しない振る舞いをする領域がある。 しかも原理が分からないから「観測すると決定する」と便宜上している。原理不明だけど分布(確率)は分かる。それが誤用されている猫箱の不確定な確率と対応してる要素だと思う。 私も噛み砕いてしか理解してないけど、猫箱が悪い例として紹介されてるのは確実です。
本物のゲームとされるvoid strangerも、張り巡らされた導線は良いけど、物語がつまらない。これを「良い」ということが気持ちいいことは理解できる。 「パクレットのウサちゃん捕獲ゲーム」の方が単純比較して複雑な構造を作っているし、きっと本物のゲーマーからシャバいと評価される「都市伝説解体センター」の方が各章の最後に漫画的な引きを自覚的に大胆に入れる演出があって、最後までプレイさせる取り組みとして新しく素晴らしかった。 集英社が絡んでるだけある。しかし内容は二重人格オチなのでやる必要ない。面白くないけど、モジュール的に良いの意。
つまり野獣七変化の方が論理的で優れている(?)。 ゲームの評価ってゲームとして下駄を履かされてるから、あまり評判と体験の質が一致しない。 こいつら<あなたが好きな他の媒体のコンテンツ>と戦っていません。だからゲーム内の相対評価もコンテンツ評とした時につまらない場合が多い。
野獣先輩がすでに原型無く変形しているのに、映像のモーフィングで動的な変形をも付与するアイデアは「量子力学に興味がないのに量子を語る子供だまし」より優れている。
コンテンツに貴賤は無い。クラシックと電子音が無機質な再生数ランキングで並ぶ昨今、淫夢と言うか音MADというか「在野の編集者」の文化はゲーム界隈よりもマジで高度になっている。 ここで見るような動きをゲームで見たことがない。私が認識する所だとまどマギ合作周辺(私はテクチャンの線形的な映像が好き)、中華圏(miziyaは好き)あたりが今熱いと思う。
https://youtu.be/8TRwHXyEY6U?feature=shared
音MADはゲームを内包できるが、ゲームは音MADを内包しない
これがいいたかった。そしてゲームは音MADを内包できる媒体なのに、なぜか近視眼的になってずっとゲームでゲームをやっている。 現状の音MAD(在野の編集文化)が面白すぎるのは、ゲームなど映像になるものはなんでも素材にできる(抽象化できる)ことを平気でしていて、コンテンツに血を捧げているからだ。 彼らはAEから映像を見ているが、ゲーム開発者は最近はgodotから映像を見ている。ゲーム開発ツールから見た世界は基本的に貧相だ。やはり抽象化、すべて抽象化が解決する。 過程にあるごちゃごちゃしたモノはすべて仲介でしかない。
これらを並べることはナンセンスのように思えるかもしれないが、媒体による軸を絶対視して評価するスタンスは本質的でない。 私が最近のインディーゲームに対して思う不満は、結局のところ、ゲームに張り合ったゲームしかないのだ。最近のインディーにフロンティアを感じない。 以前まで感じたインディーのワンダーは今はpico8、アイワナ、fnf、flashあたりにあると思う。正直、unityやgodotで作られたゲームの時点で少し薄ら寒い。
同人的倫理観を信仰し、英語圏から隔離された日本語圏はflashの終了後、センスの良いそれに触る機会が減ったのも本当に残念だ
近視眼的に、媒体の軸を限定してゲーム同士を比較し、楽しんでいる振りをしている。 正直、私にはもはやそういった軸に訴求するゲームはせずとも面白くないと思う。
淫夢より面白いゲームは無かった
これは淫夢が究極的に面白いと言っているわけではない。 ADVとかゲームであることより、エンタメ(人を楽しませる)ことに関心を持たざるを得ないジャンルなどは淫夢を超越してることもある。
ゲーマーのコンテンツ評で根本に「有ることを自体を有難がる」仕草を見るのはうんざりだ。そもそも、もし総じてつまらなかったと感じた時にそれを認められないでしょ?
根本的に「ジャンルを軸にコンテンツを比較する文化」に不満がある。 相対軸じゃなくて絶対軸の話をしてしまったので、主観盛り盛りでした。ごめんなさい。
淫夢より面白いゲームを作る
大きな目標を立てる場合、こういう標榜がいいのかもしれない。ゲームは無理にゲームを標榜しなくていいと思う。
ゲームの目的はゲームじゃなくて良い。それはプログラミングによる表現が抽象化に纏わるモノだからだ。高度な抽象化は次元を横断して世界観を作る。ゲームの場合、マルチメディアの相互干渉によって誘発される空間と状態遷移を制御する余地によって。
(2025-09-07 17:01:57)
アジア圏の音MADは世界よりも5年進んでいると思う。 memeは15年遅延してやってくるのに。
toby foxよりも圧倒的に優れた日本のインディーゲーム開発者一選
ゲーマー界隈の不満は「評価軸の制限」とあと一つある。 それは日本の死ぬほど成功したインディーゲーム開発者を圧倒的に過小評価し続けている点だ。いや現状の態度はバカにしてるといっていい。
私は心の中で彼らを千葉のnotch,パルワールド完全上位互換,hytackaの理想を体現した男,単騎でブルアカと張り合うゲーム,日本インディーゲームの王,日本で一番オープンワールドゲームを売った個人と呼んでいる。
日本のインディーゲームの王は、SAKURA School Simulator、ガルソフトが開発するオープンワールドゲームです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.garud.ssimulator
驚くべきことにandroidだけでも1億DLされている。これにiOSと233 Leyuan(中国でもランキング1位になった)を含めると圧倒的に成功を収めたインディーゲームであることが分かる。 現状、日本で最も成功しているインディーゲームだと予測している。そして最も過小評価されている。
undertaleが500万販売したとちやほやされていた時期には10倍の5000万販売していたし、ハイタカ氏のいう「世界一面白い」の面白いが指すモノを比較すれば、SAKURAはundertaleよりも10倍面白い。 無料のゲームと買い切りで比較できないと思うかもしれないが、価格設定はマーケティングであり、0円で売って、広告で稼ぐという手法の勝利とも言える。
数字で見るとゲームをする人の中でゲーマーはマイノリティーだと思う。 実際にプレイするとカオスだけど普通に面白かったです。そして「現実と私の速度を調整し、あの辛く苦しい夜を越えられる」として岡野ゆきな指数が高いゲームでした。 本当のゲームというのは岡野ゆきな指数の高いゲームのことであって、決してもう気晴らしは必要ないのに、ゲームを批評したり、気晴らしに熱中する人生の落伍者のためにはゲームは存在しない。 偽物のゲームだけが本物の人間を救うことができる。任天堂が神なのは究極の偽物と本物の救済を実現しているからだ。そういった意味でSAKURAはゲームとしての役割を効率的に果たしている。
インディー判定が厳しい人も、これは二人で開発されているものであるし、正真正銘のインディーゲームの王です。 例えスマホのやすい見た目のゲームであっても、一つのプレイに貴賤はありません。特にスマホしか娯楽のない田舎者の子供にはありがたいゲームだと思う。
https://garusoft.com/company.html
SAKURA School Simulatorは、小規模開発チーム(約2人)で1億ダウンロードを達成した日本のインディーゲーム異常成功事例
これだけは覚えておいてください。
英語は悲しみ
最近、英語学習に取り組めるようになってきた。 というのも、受験英語は非常に混乱させる原因となり、私を長らく言語学から遠ざけていたからだ。 日本では国語学と言語学で区別があって、その認識的な微小な溝が埋まらず、教育市場から漏れ出すネイティブ至上主義によって本質は霧の中へ消えた。
最近、lisp言語に触れることが多く、偶然に再帰の概念について正しい理解を得たことで、言語についての多くの誤解が取り払われるきっかけになり、理解が一気に進んだ。
レベルで言えば、2/10くらいかな。読解以外はカスで、産出レベルは脳内の思考やLLMとのやり取りしかできない(記事は苦痛)。 暗記は一切しないから語彙は少ないが、長大な本を読むと200ページ進んだ時点で辞書がいらなくなるほどすらすら読めるようになる。 創発は記憶が弱いけど、読めば瞬時に脳内で索引される程度の能力(幻想郷)です。
私が第二言語習得で感じる最大の障害は納得までの過程だと思う。英語の文章をどうやって納得するのか?私はずっと疑問だった。
this is a pen.
この文章一つ見ても、thisがpenであることが記述されてることが分かる。しかし私は納得できない安心できない。
これはペンです。
ネイティブなので日本語訳を取ると理解と納得と安心が得られる。曖昧な表現だが体験として多い。 SVOという文法を取るだけで、何か理解の作法から外れる感覚があり、一文でこれなのだから文同士の関係を考えると意味不明となる。(全ての文の意味を理解しているにも関わらず!)
英文に対面して、最終的に英文を日本語に翻訳し、初めて納得する。 結局、英語を読んでいるようで、日本語を読解していたのだった。
私にとって英語とは「日本語を暗号化した文章」でしかなかった。単語は置き換え、文法規則を変更しただけの日本語だ。
翻訳するな
I like apples
私はりんごが好きだ
この2つを比較すれば、英語を日本語で翻訳して理解することが如何に無駄な認知リソースを使っているか理解できるだろう。
文法の対応を取る。
I(主語) like(動詞)apples(目的語)
私(主題)りんご(主格)好きだ(形容動詞)
まず「Iと私」は主語と主題で機能が異なる(‘私’は主語ではない)。この時点で混乱の元である。 そして動詞と形容動詞も機能が異なる。というか何一つ合致していないのだ。
格付与と順序の規則
これらの違いを述語の関数として考えると理解しやすい
predicate("john","book","Mary")predicate = {
"ga": "John",
"wo": "book",
"ni": "Mary"
}英語は順序システムで、引数の順序と型が決まっている。それを外すとエラーになる。
日本語は格システムで、格に該当するモノを不動順に索引できる。順序を外してもエラーにならない。
この対応をわざわざ取る必要があるか?無いので英語の理解において日本語を使う必要がないし、エンジンの違いでノイズになる。
日←→英の辞書も翻訳的な便宜が乗っているだけで、概念の説明になってないことが多い。at allの意味を英英と英日で比べてみて思った。
ではどうやって理解するか?
英語を英語のまま理解するために理解しておくべきことは非常に簡単である。
- 完全文(文法的に正確な文章)
- 修飾は常に意味的制限である(修飾されるほど意味が制限される。拡張を意味する形容であっても)
- どれだけ再帰しても同じ抽象レベル(どれだけ関係節で再帰が深くなっても同じ法則が適用され続ける)
ボキャブラリーの問題は、意味的な置き換えか抽象化された構造に項を当てはめるで説明できる。
それでも分からない節を[bracket]にでも置き換えて読めば、認知負荷が過多になることは無いだろう。
When we studied [braket],
we mentioned [bracket].When we studied various ways of [bracket],
we mentioned in Section 2.3.3 [bracket].When we studied various ways of representing [bracket],
we mentioned in Section 2.3.3 the task of [bracket].When we studied various ways of representing sets in Chapter 2,
we mentioned in Section 2.3.3 the task of maintaining [bracket]. we mentioned in Section 2.3.3 the task of maintaining a table of [bracket].
we mentioned in Section 2.3.3 the task of maintaining a table of records [bracket].
we mentioned in Section 2.3.3 the task of maintaining a table of records indexed by identifying keys.
このプロセスは強制的に理解できる。翻訳で対応を取っても
[bracket]を学んだ時、[bracket]に触れた。
lispの)))))))が置換モデルによって簡単になる利点を割とそのまま扱える(英語の関係節は右結合の再帰)。
まあここまではきっと勘違いで、AST木の性質を断片的に語ってるだけ何だと思います。
THE CAMBRIDGE GRAMMAR OF THE ENGLISH LANGUAGEを読破するまでの気休めで、如何せん長いので待ちきれない。